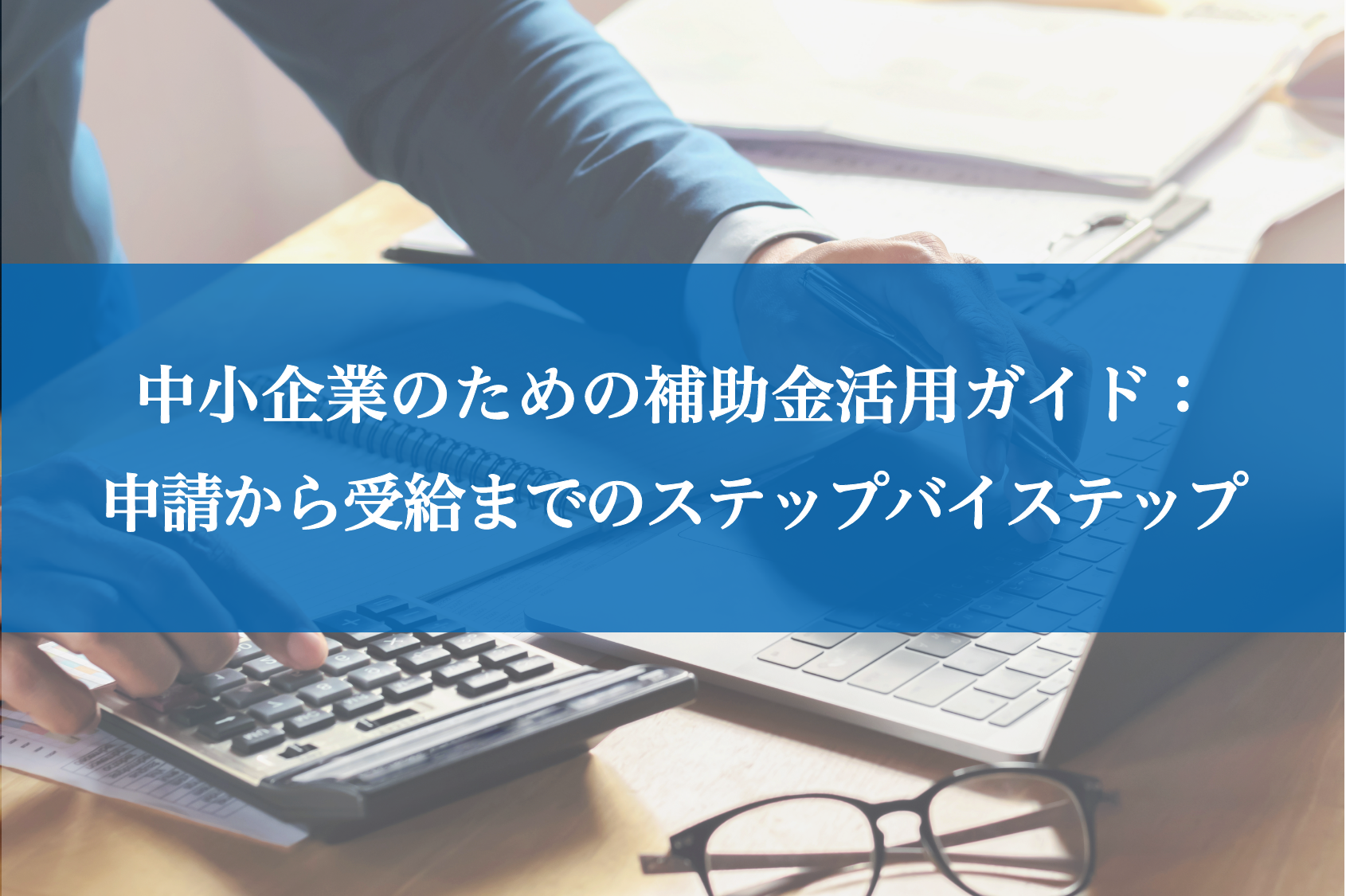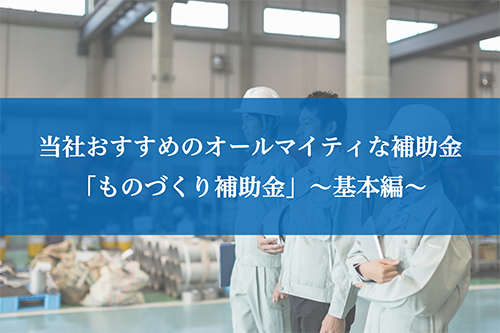行政書士法改正と補助金申請支援
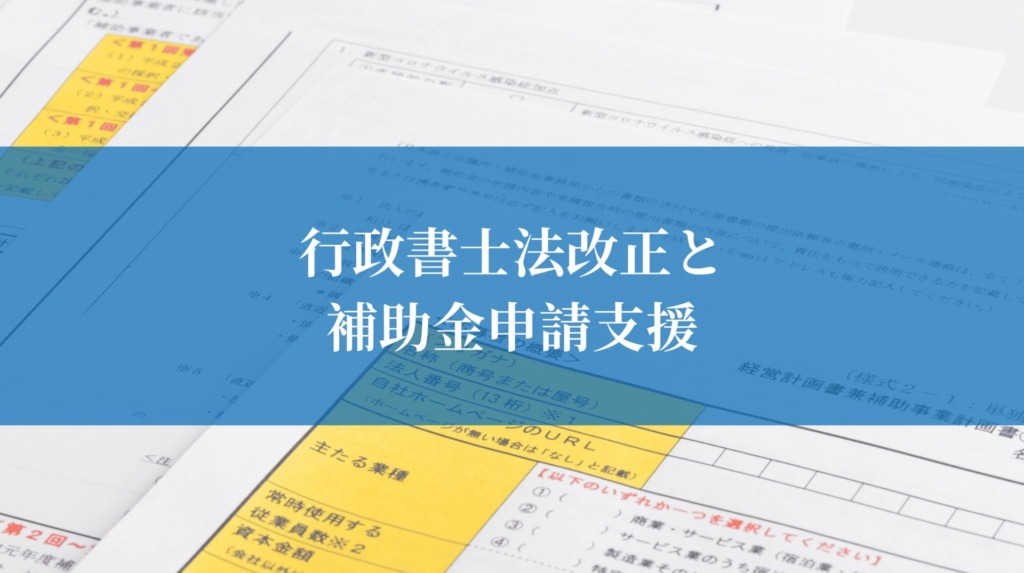
補助金支援を“誰が担うべきか”という問いに、中小企業診断士として思うこと
近年の行政書士法改正をめぐって、「補助金申請支援の一部が行政書士の独占業務に該当するのではないか」という解釈が一部で広がり、その解釈を根拠に、他士業を排除するような主張がなされるケースも見受けられるようになりました。
しかし、私たち中小企業診断士が担ってきた「事業計画の策定支援」は、あくまで経営支援の一環であり、行政手続きそのものではありません。
それにもかかわらず、「その計画書が行政への提出書類の一部になるなら、たとえ事業計画書であっても、有償での支援は行政書士しかできず、他士業が関与すれば違法である」といった極端な主張が一部でなされていることには、強い違和感と懸念を覚えます。
このような主張が広がれば、現場の実情にそぐわない制度運用がまかり通るおそれがあり、制度の健全性そのものが損なわれてしまいます。
以下に、私の考えを整理してお伝えします。
解釈のゆらぎが現場に混乱をもたらす
現在、問題となっているのは法改正そのものではなく、その「解釈」です。
一部の行政書士は、補助金の申請にあたり、行政に提出する書類であれば、たとえ事業計画書や会社紹介資料、プレゼン資料であっても、それを有償で作成(あるいは作成の一部を代行する)行為は行政書士の独占業務であると主張しています。
つまり、「文書の種類」ではなく「行政に提出されるかどうか」という目的のみを基準にして、診断士や他士業の関与を違法とするような、極端な解釈がなされているのです。
これは、「申請書類の作成代理」という範囲を大きく逸脱した、目的論による業務範囲の恣意的拡大であり、他士業の業務を実質的に封じ込めることになりかねません。
本来、補助金申請において重要なのは、申請の前提となる事業計画の質です。この「事業計画書の作成」支援は、補助金に限らず、経営支援の現場で中小企業診断士が担ってきた中心的な業務領域です。たとえば、「経営改善計画の策定支援(405事業)」などはその典型例です。
このような主張は、業際を守るというよりも、他士業の活動を排除するための手段として“制度を解釈で歪めている”ようにすら見えます。
事業計画の策定支援という「経営判断」に基づく支援と、申請書類の代理作成という「行政手続き」は、明確に線引きされるべきです。
診断士は「政策を伝える橋渡し役」でもある
中小企業診断士は、単に事業計画の形式を整えるだけの存在ではありません。
中小企業支援法に基づく国家資格として、経済産業大臣の登録を受けた「経営に関する専門的知見と実務経験を有する者」と定義されており、中小企業政策の担い手の一翼を担うことが制度上明確に位置づけられています(※中小企業支援法第11条、ならびに中小企業庁公式ページより)。
具体的には、毎年の『中小企業白書』や施策ガイドラインを通じて、国がその時々で中小企業に対して求めている方向性――たとえば「賃上げの実現」「グリーン成長戦略」「デジタル化・省力化投資」など――を把握し、それを事業者の計画に反映させることが可能です。
さらに、補助金制度に限らず、各種支援策を中小企業にわかりやすく伝え、活用を後押しする“橋渡し役”としての使命も担っており、これは行政書士や他士業とは本質的に異なるスタンスです。
このような背景から、補助金を活用したい中小企業が、診断士に支援を依頼するのは極めて合理的な選択であり、制度本来の趣旨にも合致しているのです。
「資格を取って対抗」は非本質的な対応
こうした業際リスクに対抗する手段として、診断士が行政書士資格を取得するという選択肢もあります。
実際、行政書士試験は中小企業診断士試験に比べて試験制度・合格率の面でハードルが低く、「複数資格」で自衛する診断士も今後増えるかもしれません。
しかし、これは戦術的には有効でも、戦略的には本質から外れた対応です。
制度の歪みによって、本来不要であったはずの資格取得が支援者側に強いられるのは、極めて非生産的ですし、事業者にとっても、業務の分担が煩雑になったり、補助金申請のためだけに複数の専門家を別途契約・調整しなければならなくなったりと、コストや手間が大きく増える結果につながります。
本来、ひとりの専門家が一貫して支援できるはずの業務が、「業際の都合」によって分断されることは、支援の質の低下にもつながりかねません。
現実的な対抗策 ― なぜ診断士による支援が必要なのか
補助金申請における事業計画書の策定支援は、本来、税務申告の税理士、助成金申請の社労士と同様に、中小企業診断士が専門的に担うべき業務です。
なぜなら、補助金制度の核にあるのは「経営戦略に基づく事業の立案」であり、これは単なる行政書類の作成ではなく、経営支援そのものだからです。
この支援領域を、単に「行政手続きの延長」として捉え、士業資格の有無だけで機械的に線引きしてしまえば、支援の質は大きく損なわれます。結果として、本来補助金を活用できるはずだった中小企業が、制度から取り残されてしまうおそれすらあるのです。
私たちは、こうした支援の質の低下を防ぐためにも、「誰が補助金の本質を理解し、企業とともに計画を描けるのか」という視点で、支援者を選んでいただきたいと考えています。
そして制度的にも、こうした専門的支援が正当に評価されるよう、私たち診断士自身も働きかけていく必要があります。
制度の本来の目的を見失わないために
制度は、誰のためにあるのか。
それは、挑戦する中小企業の成長を後押しするために存在しているはずです。
制度の運用が「資格保有者の権利争い」に変質してしまえば、事業者は不自由を強いられ、支援者は疲弊し、制度の信頼性そのものが損なわれます。
いま、私たち中小企業診断士は、自らの専門性と使命をもう一度見つめ直し、それを制度の中にきちんと位置づけるために、声を上げ、行動していくべき時にあるのではないでしょうか。
「資格者の縄張り争い」に終始するのではなく、支援の質と中小企業の成長という本来の目的を見据えた制度運用を
私たち中小企業診断士は、現場で培ってきた信頼と実績を武器に、これからも“本当に必要な支援”を届け続けていきたいと考えています。
この記事に関するご意見やお仕事のお問い合わせは
下記フォームよりご連絡ください
関連記事
ビジネスを前進させるサポートは、
当社におまかせください!